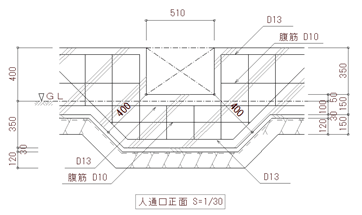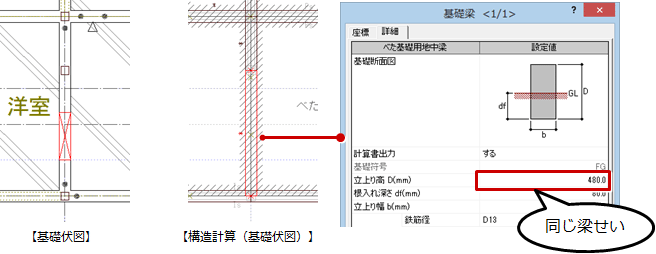| プログラム名 | 木造構造計算 | Ver. | Ver.5 | ID | Q630150 | 更新日 | 2018/12/04 |
Q:人通口があるときの基礎梁の計算について教えてください。
A:基礎梁の開口部の検討は、設計者の判断で次のいずれかの方法で行ってください。
① 人通口シンボルを入力して検討する
② モデル化して最小梁せいで検討する
③ モデル化して基礎梁と同断面で検討する
① 人通口シンボルを入力して検討する
人通口シンボルを入力する
- 「基礎」メニューから「人通口(立上り部開口)」を選びます。
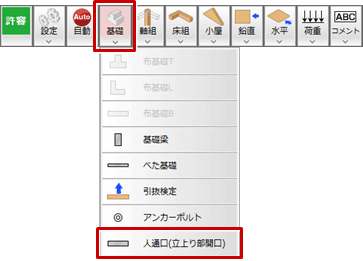
- ダイアログで開口部の有効となる躯体せい、各部位の鉄筋と本数などを設定します。
- 人通口の始点と終点をクリックします。
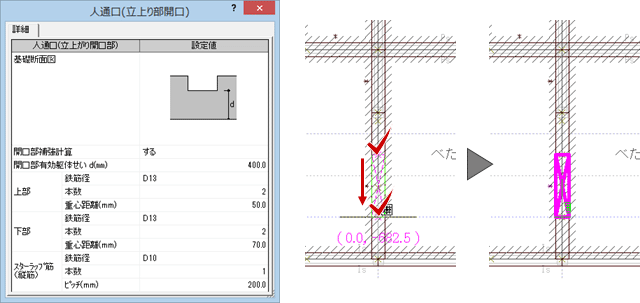
メモ
- 基礎伏図にて「基礎」メニューの「床下換気・人通口」の「人通口」で人通口シンボルが入力されている場合、木造構造計算に連動します。
- 開口部下の検討を行うには、基礎梁の算定スパン間に人通口を入力する必要があります。
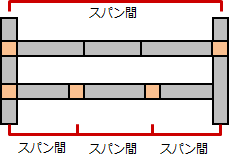
検討方法を確認して計算する
- 「初期設定:計算条件(方針)」の「◆立上り開口部下の検討方法」にて「主筋断面積比」「基礎梁応力」から開口部下の検討方法を選びます。
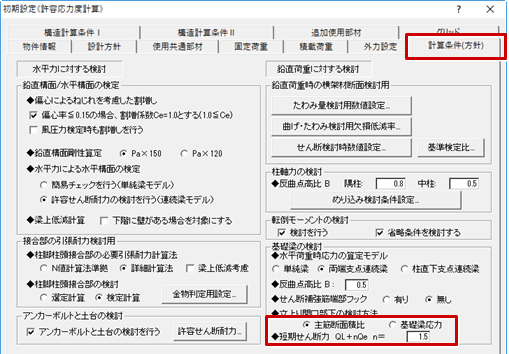
- 「構造計算」をクリックして、計算結果を確認します。

- 「構造計算結果閲覧」をクリックして、計算書を確認します。
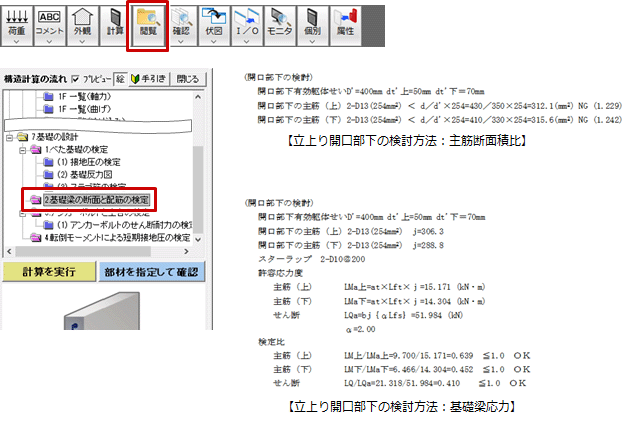
② モデル化して最小梁せいで検討する
基礎梁を最小梁せい(人通口が入る箇所の基礎梁のせい)で検討します。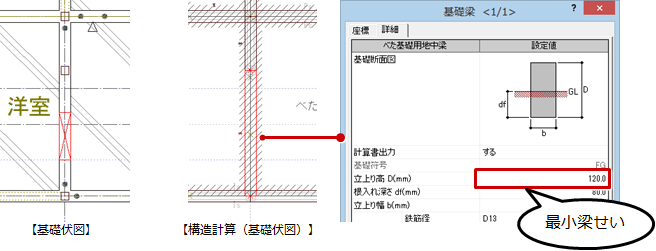
メモ
- 対象の基礎梁の端部に軸力がかからない、また人通口が十分な補強されているのであれば、この基礎梁は計算しなくてもかまいません。
③ モデル化して基礎梁と同断面で検討する
次図のように人通口部分に地中梁を設けることで、基礎梁の梁せいを保持できる場合は、同断面で検討します(梁せいはそのまま)。